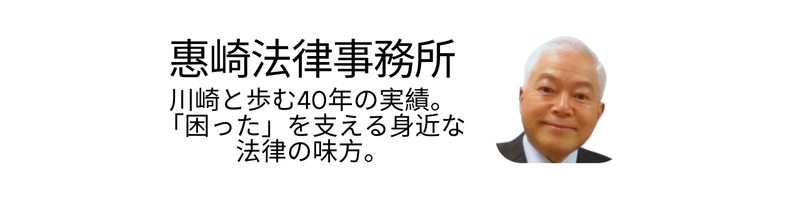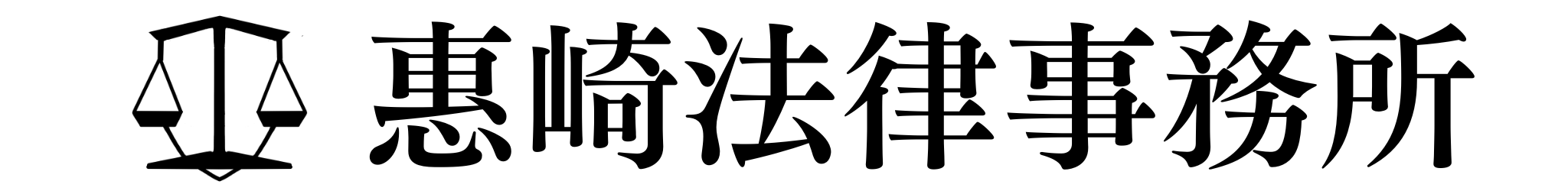令和5(受)1838 損害賠償、求償金請求事件
令和7年7月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
1 ポイントは何か?
被害者側の過失とそれに準ずる被害者の素因減額
2 何があったか?
Aが管理する駐車場の路面にへこみがあり、後退しながら駐車しようとしたB
が負傷した。
Bの弁護士費用以外の総被害額金9,412,961円➀であった。3割素因
減額で残金6,589,073円➁、そこから2割過失減額で残金
5,271,258円➂、既払額80万円④で残金4,471,258円➄で
あった。
Bが契約者であるC損保会社は人身傷害保険に基づいてBに保険金
6,663,789円⑥を支払った。同保険には、過失相殺は考慮するが、素
因を考慮しない、契約者に有利な限定支払条項があった。
BがAに対し、損害賠償請求をし、Cは⑥+➁>➀の場合にのみ求償権を取得
すると主張した。
⑥+➁―➀=3,839,901円⑦。
Bの請求額は⑥-⑦=➀-➁=2,823,888円となる。
Aは、⑥+➂-④=5,345,974円⑧の範囲内でCが求償権を取得し
、⑧>➄で、BのAに対する請求額は0円と主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
B敗訴。
Cは、⑥か➂のいずれか少ない額について損害賠償請求権を代位取得する。⑥
か➂のいずれも>➄で、BのAに対する請求額は0円。
(裁判官林道晴の補足意見)、素因減額は、基本的には、被害者に対する加害
行為と加害行為前から存在していた被害者の疾患とが共に原因となった場合に
おける損害額の発生そのものに係り、発生した損害額について公平な分担のた
めの調整を図る過失相殺とは局面が異なるのであり、同様に解することはでき
ない。
4 コメント
人身傷害保険の約定が契約者に有利に定められていても、それが加害者にも通
用するわけではない。