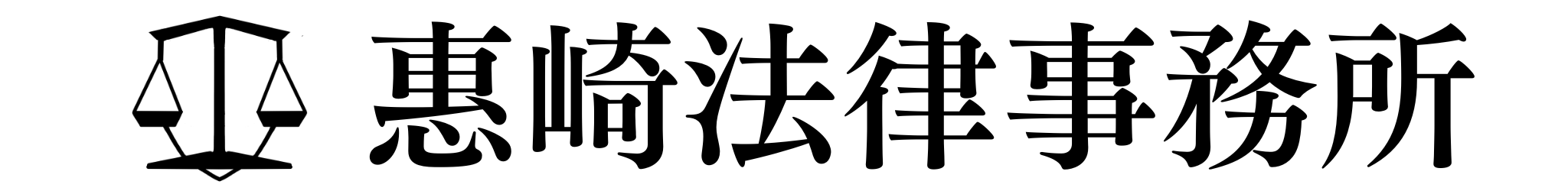1 ポイントは何か?
無償で被相続人の療養看護をし、被相続人の財産を維持増加した親族(相続人、相続放棄者、欠格者,被廃除者は除く。)は、特別寄与者として、相続人に対し寄与に応じた額の特別寄与料の請求をすることができる(民法1050条1項)。家庭裁判所に審判を求めることができる期限は、相続開始から1年以内で、相続開始及び相続人を知った時から半年以内である(同法2項)。特別寄与料の額は、相続財産から遺贈分を差し引いた範囲内で、家庭裁判所が一切の事情を考慮して定める(同条3項、4項)。相続人が複数いる場合は、遺言書があれば遺言書で定まった割合、なければ法定相続分の割合により負担する(同条5項)。本件は、被相続人の療養看護をした息子の嫁が被相続人の他の息子に、特別寄与料を支給した。しかし、特別寄与料分担請求を受けた息子は、被相続人の遺言書で相続分がなく、いる分減殺請求権を行使して、法定相続分の半額を確保していた。この場合、特別寄与料の分担を求めることができなかった。
2 何があったか?
無償で夫Aの親である被相続人Bの療養看護をした妻Cが、被相続人の財産を維持増加した親族であり、相続人、相続放棄者、欠格者,被廃除者ではないので、特別寄与者として、相続人に対し特別寄与料の請求ができる立場であった。
Bは、Aにすべて相続させるとの遺言書を残していた。
Aの弟Dは、遺留分減殺請求を行使した。
そこで、Cは、Dに対し、遺留分減殺請求権を行使して確保した相続分の割合による特別寄与料の分担請求をした。
3 裁判所は何を認めたか?
C敗訴。
Dの相続割合は、遺言書で定めた0円でしかなく、遺留分減殺請求権の行使の場合は規定がないので、Cは、Dに特別寄与料を請求することができない。
4 コメント
Bが、親族でないEに全部遺贈する遺言を残していたとしたら、A及びDは遺留分減殺請求権を行使することによって、それぞれ法定相続分の半分を確保できるが、Cは何も請求できず、泣き寝入りするほかないことになるのか。CがBの親族でなければ、特別寄与料は発生しない。この特別寄与料の制度設計は果たして合理的なのか疑問を感じる。
これは、これからの少子高齢化社会を考えた時に、親族間での、相続関係を超えた助け合いの新しいスタイルとしてクローズアップされるだろう。
少子高齢化社会では、一方では、若い人々と協力できる元気な老人や、障害を乗り越えて健常者以上に能力を発揮しながら生きている人々が増えている。他方では、親族の誰にも面倒を見てもらえず、また地域社会から孤立せざるを得ない老人や障害者も増えている。後見制度は、意思能力の補充や財産管理には役立っても、身上監護の面では、それほど役に立たない。現実を見ると、市町村の高齢者・障害者支援課、地域包括支援センター、ケアマネジャー、老人施設などが役割を分担しながら、支えているのが現状である。これらの支援に期待しながらも、総合的、機能的な身上監護支援者制度の設計図が待たれる。
判例
令和4(許)14 特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和5年10月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
お悩みの方
相続は故人の財産や権利を後継者に引き継ぐ制度ですが、トラブルを避けるためには生前に意思を明確にしておくことが大切です。これには遺言が有効です。しかし、遺言がない場合も法律で公平な遺産分割が保障されています。遺言作成、内容に関する悩み、遺産分割、相続人の不明、祭祀財産の承継、相続放棄、故人の負債に関して困っている方は、川崎市の恵崎法律事務所までご相談ください。