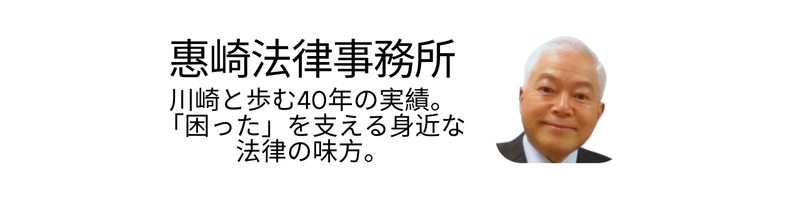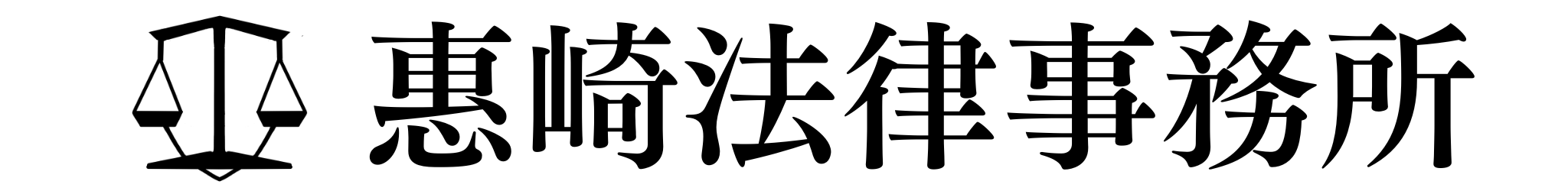広島高等裁判所和37(ラ)33 財産分与審判に対する即時抗告事件昭和38年6
月19日判決
1 ポイントは何か?
内縁解消の場合に財産分与の請求ができるか。
2 何があったか?
AはBとの内縁解消に際し、Bに対し財産分与を請求する調停を申立てた。
Bは、法律上の婚姻についてのみ財産分与を請求しうると主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
A勝訴。
原審家庭裁判所は、Bに対し、Aへの財産分与を命ずる審判を下した。
これに対しBが即時抗告をした。
広島高等裁判所は、Bの抗告を棄却した。
同高等裁判所は、民法の法律婚主義を前提に、次のような注目すべき理由を述
べる。
氏の変更、出生子の嫡出子たること、姻族関係、配偶者相続権の発生等の婚姻
の効果は内縁については認めるべきではない。けだし、これらは戸籍法による
婚姻の届出を前提とするものであり、かつ夫婦以外の第三者の身分関係にも影
響を及ぼすものであるから。
これに反し、夫婦間の同居、協力、扶助の義務、婚姻費用の負担、日常家事債
務の連帯責任、帰属不明財産の共有推定、婚姻解消の際の財産分与請求権の発
生等の婚姻の効果は、いずれも内縁についてもこれを認めてしかるべき(婚姻
費用につき最高裁判所昭和32年(オ)第21号、同33年4月11日第二小
法廷判決)。けだし、これらは夫婦間の共同生活関係自体を規整するものであ
つて、これによって第三者に不利益を与える虞れもないから。
「財産分与の本質は第一義的には離婚の際における夫婦共同生活中の財産関係
の清算であり、第二義的には離婚後の扶養及び有責配偶者から無責配偶者に対
する離婚に伴う損害の賠償であると解されるが、そうだとすれば、財産分与は
、婚姻の解消を契機としてなされるものではあつても、現に存した夫婦共同生
活関係を最終的に規整するものともいうべく、かつこれによって直接第三者の
権利に影響を及ぼすものではないから、内縁についても、これを認めるのが相
当である。
この点に関し、内縁配偶者の相続権の有無が、権衡上一応考慮されるが、右相
続権の有無は当然他の相続人の権利に影響を及ぼす関係上、その地位の公示が
望まれる点において財産分与請求権とは異る面を有するから、内縁配偶者の相
続権が否定せらるべきであるとしても、同様にその財産分与請求権が否定せら
れるべきであるとの論拠にはならない。
そして、右の解釈は,死別における内縁配偶者は、相手配偶者からの生前贈与
、遺贈等により、或いは相手配偶者の相続人からの法律上または事実上の扶助
によりその地位を保護されることを予想し得るに反し、不和による内縁解消に
おける配偶者は右の如き保護を通常期待できない点からみて、内縁配偶者にと
つては相続権以上に財産分与請求権を必要とする事情が切実であるという実際
問題にもこたえるものであると考える。」
4 コメント
本判決によれば、第三者の身分関係に影響を及ぼす場合は法律形式主義が尊重
され、そうでない場合は、実質主義を貫いてよい。このことは、法律解釈の広
い範囲に拡張しうるのではないか。学生時代に、椿寿夫教授から、「法律の解
釈とは、場合を分けることだ。」と聞いた記憶がある。