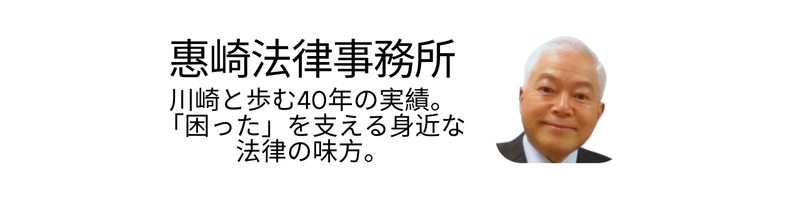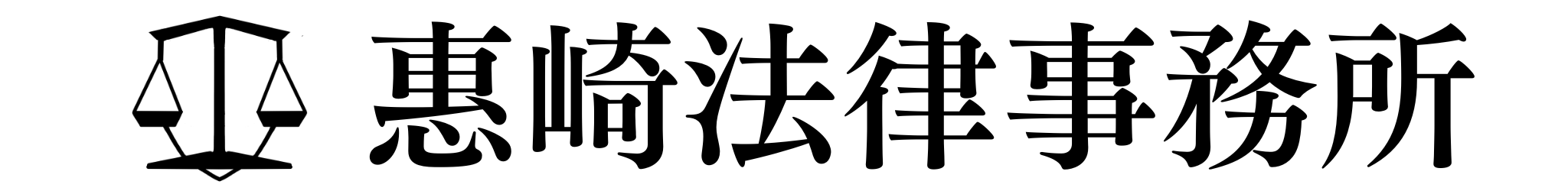名古屋地方裁判所平成29(行ウ)72 遺族補償一時金不支給処分取消請求事件
令和3年10月11日判決(A遺族敗訴)
名古屋高等裁判所令和3(行コ)70 遺族補償一時金不支給処分取消請求控訴
事件 令和5年4月25日判決(A遺族逆転勝訴)
1 ポイントは何か?
自殺の業務起因性、判断枠組、業務の質的加重性、パワハラ。
2 何があったか?
Aは、B社に平成22年4月就職後、同年10月28日頃何らかの精神障害を
発病し、その後自殺した。
Aの遺族らが、津労働基準監督署長に対し労働者災害補償保険法による遺族補
償一時金の支給を申請したが、平成26年9月26日付けで支給しない旨の処
分をした。
Aの遺族らが、国を被告として、その処分の取消を求め、裁判所に提訴した。
3 裁判所は何を認めたか?
Aの遺族らは地方裁判所では、Aが受けた業務上の精神的負荷は「中」である
とされ敗訴したが、高等裁判所では、「強」であると認定され、逆転勝訴した
。
業務起因性の有無については、当該疾病等の結果が、当該業務に内在又は通常
随伴する危険が現実化したものと評価し得ること、すなわちストレス-脆弱性
理論を前提とし、同程度の年齢、経験を有し、日常業務を支障なく遂行するこ
とができる平均的労働者を基準として、社会通念上客観的にみて、精神障害を
発病させる程度に強度であるといえる場合に、当該業務と精神障害の間に相当
因果関係を認めるのが相当である。そして、厚生労働省は、精神障害の業務起
因性を判断するための基準として認定基準を策定しているところ、その作成経
緯及び内容等に照らしても合理性を有するものといえるから、その内容を参考
にしつつ、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断するのが相当というべき
である。同認定基準は、①対象疾病の発病があったこと、但し、世界保健機関
が定める国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神および行
動の障害」に分類される精神障害のうち、器質性のもの及び有害物質に起因す
るもの以外で、発病時期及び疾患名を、「臨床記述と診断ガイドライン」に基
づき医学的に判断する。②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務によ
る強い心理的負荷が認められること、但し、いじめやセクシュアルハラスメン
トのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体
のものとして評価することから、発病の6か月よりも前に開始されている場合
でも、発病前6か月以内の期間にも継続していれば、開始時からの行為を評価
する。③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは
認められないこと。
本事案で、高裁は、パワハラの事実についても詳細に認定し、「本件労働者は
、新入社員で あり現場実務能力がないのにその能力を超える責任の重い過大な
業務を課され、周囲の支援態勢等がない中で複数の業務を同時並行して行わざ
るを得なくされ、さらに上司からパワーハラスメントを受けたことによる業務
上の心理的負荷により精神障害を発症し本件自殺に至ったことが明らかである
から、本件労働者の精神障害の発病及び死亡は業務に起因するものである。」とした。
4 コメント
裁判所は、厚労省基準を基本としている点で、行政主導型、行政追認型の裁判
であり、この点では、むしろ、行政を厳しくチェックすべきである。ところで
、Aの遺族らからB社を被告とする損害賠償請求訴訟が別途提起されたかは不
明である。