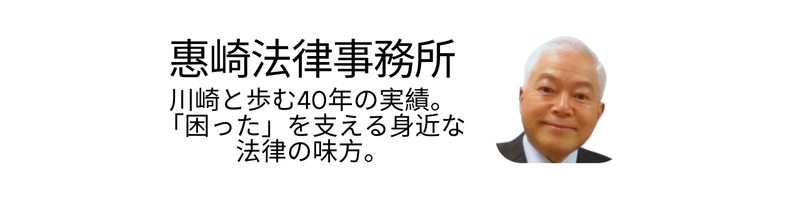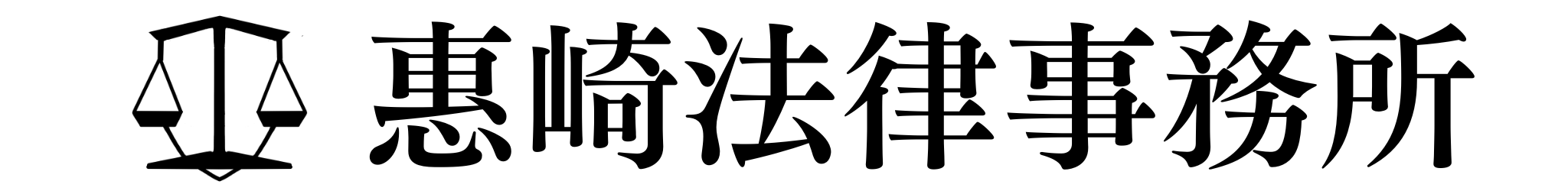最高裁判所第一小法廷 令和6(受)239 婚姻費用の合意無効確認請求事件
令和7年9月4日判決(原審:東京高等裁判所)
1 ポイントは何か?
婚姻費用合意の効力を審理する裁判所。
2 何があったか?
Aは、Bと別居し、A・B間で離婚までの婚姻費用分担合意をしたが、Aは、Bの収入から考えてこの合意では安すぎることがわかったので、増額の調停を東京家庭裁判所立川支部に申立てたところ、家庭裁判所は申立日からの増額の審判を下したが、婚姻費用分担合意日から増額調停申立日までの間の増額を認めなかった。Aは、家庭裁判所に婚姻費用分担合意日からの増額を認めさせるためには、どうすればよいかと考えた。家庭裁判所に求めるべきか、地方裁判所に求めるべきか。Aは、増額を命ずるのは家庭裁判所の役割だが、その前提として、合意書の無効を確認する訴訟を地方裁判所に提起する必要があると考えて、それを東京地方裁判所立川支部に提起した。
3 裁判所は何を認めたか?
地方裁判所はAの請求が確認の利益を備えていない不適法な裁判であるとして却下した。しかし、Aが控訴し、東京高裁は、この判決を取消し、地裁に差し戻した。そして、最高裁判所は、高裁判決を破棄し、Aの控訴を棄却した。これにより、家裁は、婚姻費用分担審判の前提事項として合意の効力を審理する権限が確認された。今後は、家裁に婚姻費用分担調停申立するとき、本判例を引用しつつ、前提問題として合意の無効確認を求めたらよいということになろう。
4 コメント
地裁と家裁の役割分担の厳格性のため、回りくどい。本判例により、家裁は、婚姻費用分担額決定の前提事項として婚姻費用分担合意無効についても判断できること、地裁の権限ではないことが明確になった。しかし、制度利用者の立場としては、地裁でも家裁でも、いずれかを選んで申立てをすれば、地裁なら証拠主義、家裁なら後見主義と手法は異なるが、いずれでも判断を受けることができるという制度設計を期待するのではないか。これは司法における利用者第一主義である。