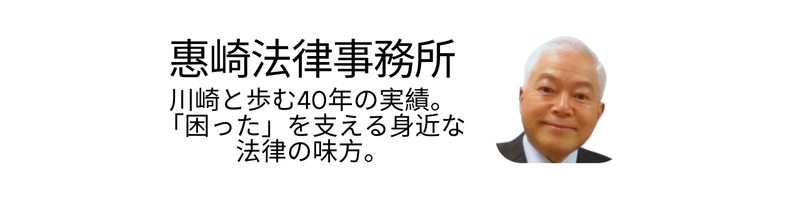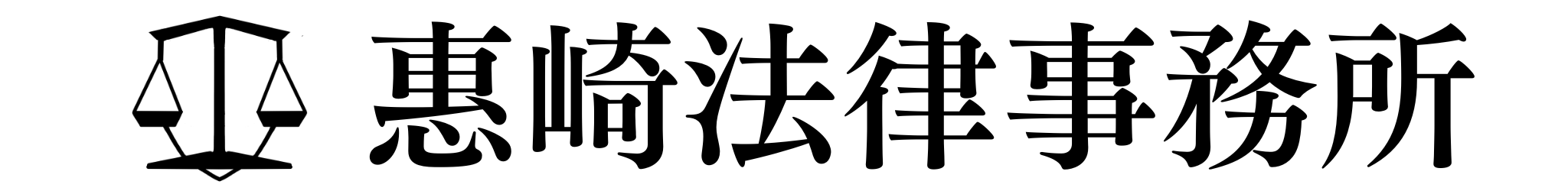最高裁判所第一小法廷 平成19(受)1987 保険金請求事件 平成21年6月4日判決 (原審名古屋高等裁判所)、
1 ポイントは何か?
隣接する建物等のそれぞれを目的とする複数の保険契約相互の関係
2 何があったか?
Aは、建物1(保育園)、建物2(老人ホーム)、及び別件建物(診療所)を所有し、B保険会社との間で建物1及び建物2を目的とする店舗総合保険契約を、C保険会社との間で別件建物につき他の店舗総合保険契約を締結していた。これらの建物が水害に遭い、Aは、Bに対して100万円の水害保険金を請求したところ、B社は、建物1、建物2、及び別件建物が、保険約款14条4項3号の「1構内」にあるので、水害保険金100万円をBとCで分けて50万円ずつ負担すべきであると主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
保険約款の解釈は難しいが、地方裁判所は、AのBに対する請求100万円を認め、これに対し、高等裁判所はBの主張50万円を認めた。
しかし、最高裁判所は、高裁判決を破棄し、AのBに対する請求100万円を認めた。Bが主張する保険約款14条4項(複数の保険で負担を分ける)は、同じ目的物件について複数の保険契約がある場合に適用されるべきで、Bの契約とCの契約は目的物件を異にするので適用されないと判断した。
裁判官涌井紀夫は補足意見で、「1構内」とは一般人の通常の理解に照らして判断すべきで、建物1及び建物2と別件建物の間は公道やフェンス、植え込みで仕切られており、1構内にあるとは言えないとした。
裁判官宮川光治は補足意見で、「本件約款は,損害保険料率算出団体に関する法律によって設立された損害保険料率算出機構作成の標準保険約款によっているが,・・・契約者である市民の合理的意思と乖離しない,分かりやすい約款の作成と保険実務における消費者保護の精神に沿った約款の解釈・運用が望まれる」とある。
4 コメント
補足意見が面白く、参考になる。保険約款の解釈は、一般人の普通の理解、消費者保護の精神によるべきという。素人的解釈を大切にしよう。