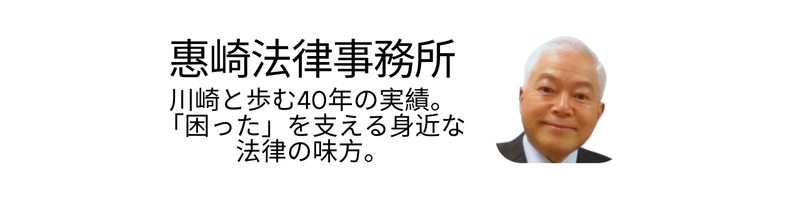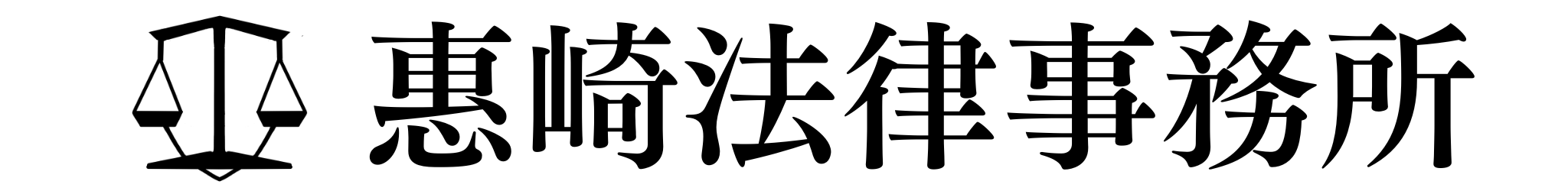東京地方裁判所 平成24(行ウ)104 所得税の決定処分及び無申告加算税の
賦課決定処分取消請求事件 平成25年10月18日判決
1 ポイントは何か?
特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言書で何も相続させてもらえな
かった相続人は相続分0の指定を受けたことになるか。そうであるとしても遺
留分減殺請求権の行使により指定相続分は遺留分の割合に変更されるか。また
、変更された指定相続分により被相続人の所得税を承継するか。
2 何があったか?
Aは、妻C、子DないしGに特定の不動産等を相続させる旨の遺言書を残して死
亡した。Xは、Aの子Bの代襲相続人であるが、Aの遺言書にはXに相続させる財
産の記載はなかった。そこでXは、他の相続人らに対し遺留分減殺請求権行使
の意思表示をした。Xの法定相続分は10分の1であり、遺留分はその2分の
1で、20分の1であった。
Aには、死亡前年分の不動産賃貸による不動産所得、株式配当所得、給与所得
、雑所得、株式譲渡所得等合計21億2031万2219円があり、所得税と
して納付すべき額は金2億7988万7100円であった。
Y税務署長は、国税通則法5条1項、2項によりXがAから承継した所得税を代
襲相続人の相続分すなわち被代襲者Bの法定相続分である10分の1により
、2798万8700円と決定した。
これに対しXが審判請求をし、国税不服審判所長の裁決は、Aの遺言書にはXの
相続分0の指定があり、Xの遺留分減殺請求権の行使の結果、Xの指定された相
続分は20分の1となるとし、Y税務署長の決定を一部取消し1399万
4300円(100円未満の端数控除)とした。Y税務署長は、それをもとに金
277万3千円の無申告加算税の賦課決定もした。
Xは、裁判所に、Y税務署長(国)の各処分の取消しを請求した。
Yは、Aの遺言書は遺産のうちの特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺
言であり、特段の事情のない限り遺産分割方法を定めたものであり(平成3年
4月19日最高裁第二小法廷判決)、相続分の指定は分数的割合をもって定め
られているものをいい、Xについて相続分0の指定はないから法定相続分10
分の1によるべきであるが、仮にXの指定相続分が0であったとしても、Xの
遺留分減殺請求権の行使により遺留分20分の1が修正された指定相続分にな
ると主張した。
3 裁判所は何を認めたか。
X勝訴。
裁判所は、YがXに対してした所得税決定のXが収める額の0円を超える部分及
び無申告加算税賦課決定を取消した。
Aの遺言書はXの指定相続分を0とするものであり、これによりXが相続する所
得税も0円である。
また、遺留分減殺請求権の行使によってXに当然に帰属した権利は遺産分割の
対象となる相続財産としての性質を有しないものであり、Xの指定相続分0が
変更されることはなく、Y税務署長のXが収めるべき所得税額を0円と決定しな
かったのは違法である。したがって、無申告加算税も課すことはできない。
4 コメント
遺言書の書き方の参考になる。
例えば、全財産を特定の相続人に相続させる場合は、他の相続人等の指定相続
分はいずれも0となるだろう。その場合は、被相続人の所得税は全部特定の相
続人が負担することになるだろう。
しかし、いくつかの特定の財産を幾人かの特定の相続人にそれぞれ相続させる
遺言の場合は、何ももらえない相続人だけ指定相続分が0となり、他の相続人
は遺産分割方法の指定を受けているが、分数的割合で表される相続分の指定は
受けていないので、被相続人の所得税の承継については、遺言書中に特段の定
めがあればそれによるが、それがなければ基本的には遺産がもらえる相続人等
が各自の法定相続分の割合で、指定相続分0の相続人の法定相続分も分担する
ほかないことになろう。
それによらず、遺産をもらえる相続人同士の話し合いで決めるとすれば、実際
にもらえる特定財産の価額の割合により所得税を負担するのが平等で合理的で
あると思うが、そうするためには不動産や動産や株式等をどう評価するのが妥
当か等の問題も話し合うことが必要となろう。