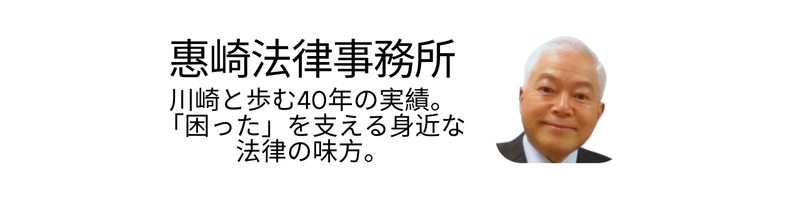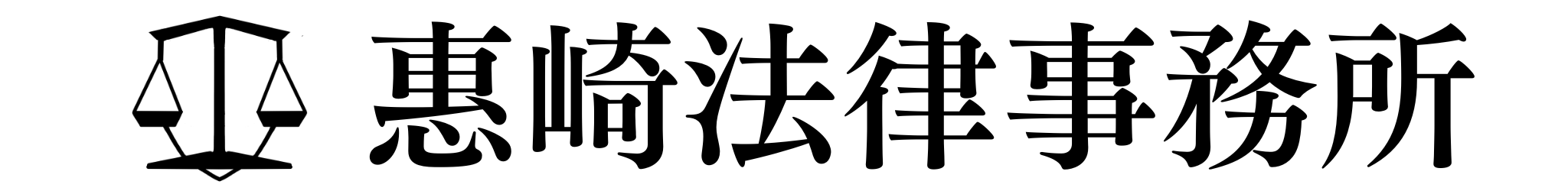東京高等裁判所 医療費返還請求事件 令和2年6月X日判決
出典は総務省131回行政改善推進会議の資料
1 ポイントは何か?
生活保護費の返還請求に応じる必要があるか。
2 何があったか?
Aは認知症で身寄りがなく病院に運ばれ即時入院となり、福祉事務所が職権
で生活保護医療扶助を決定したが、その場合、国民健康保険及び後期高齢者医
療制度の本人負担割合1割の制度は適用除外となり、生活保護担当者は病院に
入院治療費全額の490万円を支払った。A死亡後、Aに相当の資力があるこ
とが判明し、自治体Bが亡Aの相続人Cらに対して金490万円の返還を請求
した。
Cらは、国民健康等が適用されていたら認められていた本人負担割合1割に
相当する49万円を超える請求の棄却を求めた。
3 裁判所は何を認めたか?
地方裁判所はBの490万円の請求を認めたが、Cらが控訴し、東京高等裁
判所は地裁判決を取り消し、Bの請求の内49万円のみ認めた。
保護を受けた場合の保護の内容を説明して十分な理解が得られていることが
返還請求の不可欠の条件であるという。
4 コメント
福祉事務所が職権で生活保護医療扶助を決定した時点で国民健康保険及び後期
高齢者医療制度の本人負担割合1割の制度が適用除外となることが問題だ。本
判決は、本人にとっては予想外の負担となる場合、本人ないしその相続人を保
護する必要があるというものである。相続財産中に十分な返還資力が残されて
いる場合はどうだろうか。福祉事務所長に保護者を探して事前の説明を行うべ
き責任を科すことは、緊急性がある場合の保護決定を遅らせることにもなりか
ねないので妥当とは言えないのではなかろうか。むしろ、緊急保護決定の負担
はなるべく軽くし、後に被保護者が有資力者であることが発覚し返還請求の要
否を検討すべき段階において、東京地方裁判所平成27(行ウ)625 生活保護返還
金決定処分等取消請求事件平成29年2月1日判決086893_hanrei.pdfが示した総
合的具体的基準を当てはめて検討すべきではないか。