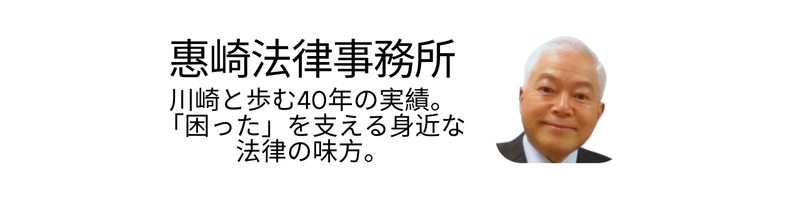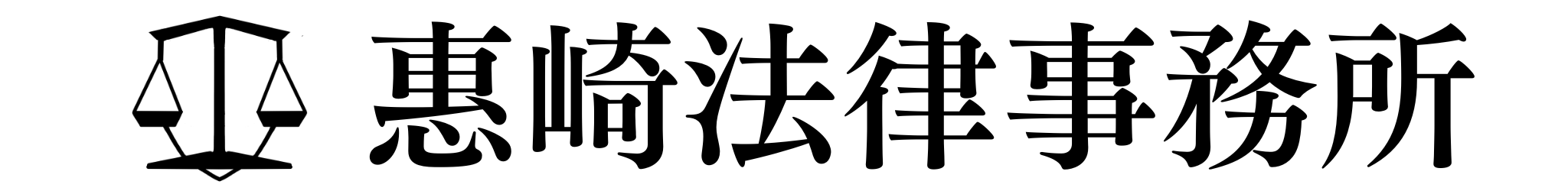最高裁判所大法廷 昭和47(あ)1896 道路交通法違反、業務上過失致死昭和
49年5月29日判決 (原審、東京高等裁判所)051047_hanrei.pdf
1 ポイントは何か?
酒酔い運転と業過致死は二つの行為として刑を加重すべきか。
2 何があったか?
Aは酒酔運転をし、交通事故を起こして人を死亡させた。
検察官は、酒酔い運転と業務上過失致死を、運転行為と事故を起こす行為の2
つの行為の併合罪(刑の加重関係)として起訴した。
Aは、罪名は2つでも運転は1つの行為であり、1つに吸収して処罰すべきで
あると主張し、居眠り運転と業過致死事件を観念的競合(刑の吸収関係)とす
る最高裁第1小法廷昭和32年(あ)第2377号同33年4月10日決定を
引用した。
3 裁判所は何を認めたか
高裁、最高裁とも、検察官の主張どおり、2つの行為の併合罪としてAを加重
処罰した。最高裁大法廷においてAが引用した居眠り運転事故最高裁判例を変
更した。
(最高裁の判断、多数意見)1個の行為とは、自然に見て社会的に1個の行為
をいう。酒酔い運転は継続的な行為であり、業務上過失致死は一時、一場所の
行為であるから、両者を1つの行為とみなすことはできない。
(裁判官岸盛一の補足意見)ドイツでは1個の行為と言うためには協働作用関
係があることを必要とし、犯罪の数だけ処罰するのが原則であるが、東洋思想
では、吸収、統一するのが原則である。わが国では併合罪加重も観念的競合も
事案に即して量刑し、必ずしもどちらが重いとは言えない。わが国の「原因に
おいて自由な行為」理論は業過致死傷にも適用され、運転前の飲酒行為に故意
過失を認めるので、ドイツ法のように飲酒運転行為を業過致死傷の過失の源と
して一体行為と考える必要はない。
(裁判官天野武一の補足意見)岸、江里口補足意見に同調。
(裁判官江里口清雄の補足意見)泥酔状態と酒酔い状態の区別はあいまいで、
酒酔い乾式カードの大雑把な質問項目だけで併合罪と観念的競合に分けられて
いる現状がある。
(裁判官岡原昌男の反対意見)⑴罪数論は、吸収・加重・併科などの科刑論で
もあり、立法政策の問題でもある。
⑵観念的競合と併合罪の判例は、事案に応じた妥当な解決を追求してきた。
⑶➀行為は自然的観察だけで客観的に個数を決めることができるか疑問。➁行
為者の主観的事情、意図目的、保護法益、行為の結果など総ての事実を社会的
現象として総合判断し、無理なくありのままに観察し、ある行為をまとめて一
個と見ることができるか。➂一個と見て最も重い犯罪の刑だけで処断すること
が相当であるか。④その行為の重なり合いが、重要部分が重複しているか。➁
ないし④が是なら、行為が一個と見て観念的競合とし、然らざる場合は併合罪
と判断するのが相当。
⑷道交法違反の酒酔運転と業務上過失致死傷事件について、➀酒酔い運転避止
ないし中止義務に敢えて違背して運転を継続する限り道交法違反は継続し、か
つ、業過の関係で運転中止義務に違背した過失行為は引き続いて存する。➁そ
の義務違背運転を原因として人身事故を起した場合には、その運転行為は観念
的競合の一個の行為と見るべき。➂なぜなら業過致死傷についても責任と行為
の同時存在が要請されるから。
4 コメント
日本法とドイツ法の違いを背景に、最高裁判事らが闘わせる行為と科刑につい
ての議論。行為をどう見るか、罪数、科刑方法の違いにも注意。この判例は、
刑事判例の読み方を一段高めてくれた。但し50年前の裁判例だから、その後
の日本、ドイツその他諸国の理論が同進展しているか、折に触れて確かめる必
要がある。
以上