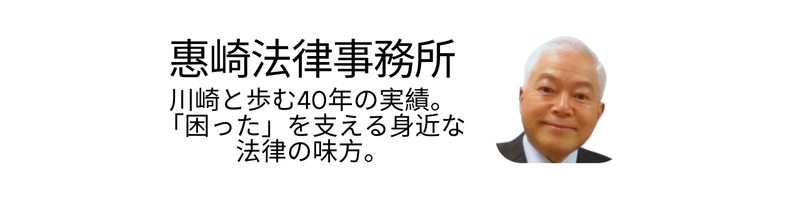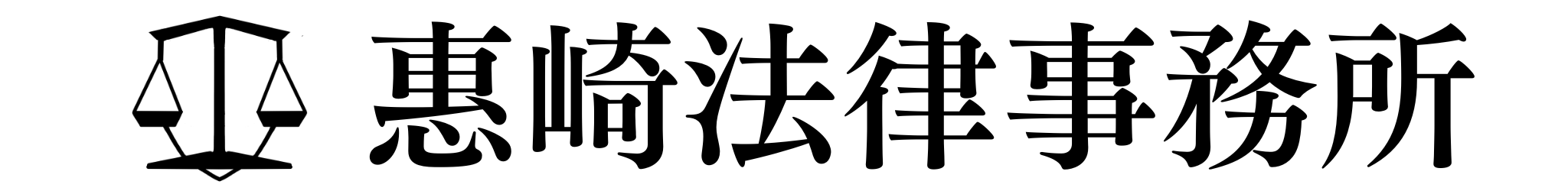知的財産高等裁判所 令和7(ネ)10022 発信者情報開示命令の申立てについ
ての決定に対する異議の訴え控訴事件令和7年7月30日判決(原審、東京地方裁
判所)
1 ポイントは何か?
発信者情報開示の条件
2 何があったか?
Aの作品動画がビットトレントネットワークにアップロードされ著作権を
侵害されたとして、Aが東京地方裁判所に、電気通信事業者Bに対しいわゆる
プロバイダ責任制限法に基き発信者情報の開示を求める申立をし(令和5年(
発チ)第10082号発信者情報開示命令申立事件)、調査会社Cの再生試験
報告書を証拠として提出した。
Bは、「プロバイダ責任制限法に基づく開示請求においては権利侵害が明
白であることが開示要件となっており、その要件を厳格化した趣旨は、発信者
情報が発信者のプライバシー及び通信の秘密と深く結びついた情報で、一旦、
開示されると事後的に元に戻すことはできず、発信者に与える不利益が極めて
大きいため・・・原判決別紙動画目録記載のIPアドレスやタイムスタンプ等
で特定される通信と再生試験の対象となったピースを送信した通信の同一性は
客観的に明らかであることが求められる。」、本件では、両者間に4秒の差が
あり、通信の同一性が客観的に明らかであるとは言えないと主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
A勝訴、B敗訴。
⑴ 東京地方裁判所は、Aの申立てに基づき、令和6年5月23日、発信者
情報開示を決定した(決定)。
⑵ Bが、東京地方裁判所に、Aを被告として異議申し立てをした(異議の
訴え)が、東京地方裁判所はAの異義を認めず、決定を認可する判決をした(
原判決)。
⑶ Bが、知的財産高等裁判所に、Aを被控訴人として控訴したが、知的財
産高等裁判所はBの控訴を棄却した。
4 コメント
発信者として情報開示されると、損害賠償請求で争うことは相当困難にな
ると思われる。発信と保存の4秒の差は、技術的には起こりうるとしても、万
一ということはないのか。難しい問題だ。