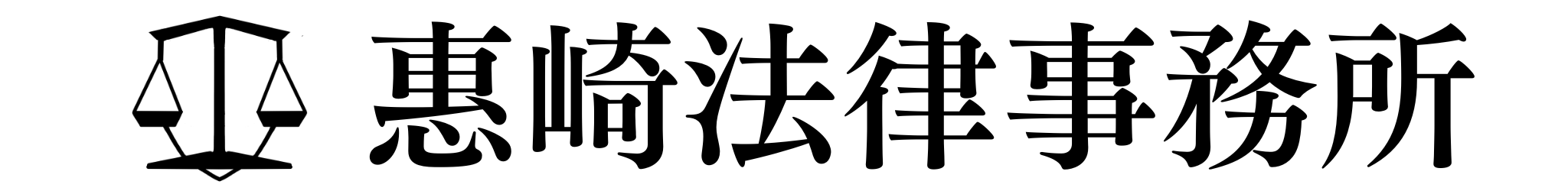ハラスメントの種類
ハラスメントとは、他人を不快にさせたり、その人間の尊厳を侵害したり、その人の意思に反して行動して脅したりする行為で、「いじめ」や「嫌がらせ」に相当するものです。 ハラスメントには、パワハラ、セクハラ、マタハラなどがあります。
ハラスメントになりうる事例
- 性的な言動による「いじめ」や「嫌がらせ」
- 職場における不合理な身体的または心理的ストレスによる「いじめ」や「嫌がらせ」
- 妊娠・出産・育児を理由とする女性労働者への「いじめ」や「嫌がらせ」
- 育児制度を使用した男性労働者への「いじめ」や「嫌がらせ」
ハラスメントについての会社の責任
会社は、労働者のために安全な労働環境を提供する責任や、労働者が相互にハラスメントをしないように監督し教育する責任があります。ハラスメントは、会社がこれらの責任を十分に果していないために起こる場合もあります。そのような場合、会社がハラスメントを受けた労働者に対して損害賠償義務を負うことがありえます。そして、ハラスメントの被害を労働災害として補償を受けることができる場合もあります。
ハラスメントをされたらどこに相談するか
会社の人事
職場内でハラスメントが発生した場合、最初に相談を検討するべきは会社の人事部です。会社の人事部は従業員の働きやすさを守るために存在し、ハラスメント問題を解決するための手続きや規定を持っているはずです。
行政の労働相談窓口
労働局や労働基準監督署には労働相談窓口が設置されています。ハラスメント問題だけでなく、賃金や労働時間など、労働に関する全般的な問題について相談することができます。
労働組合の相談窓口
労働組合に加入している場合、その組合の相談窓口を利用することができます。組合は労働者の権利を守るために存在し、個々の労働者の権利を守るために活動しています。
労働委員会の相談窓口
労働問題について調査・審議し、紛争解決を図るための公的な機関です。不当な労働条件や解雇、ハラスメントなど、様々な労働問題について相談が可能です。
裁判所の相談窓口
裁判所には法律相談窓口が設けられており、法的な問題について無料で相談することができます。ハラスメント問題を法的に解決するための情報やアドバイスを得ることができます。
弁護士会/日本司法支援センター(法テラス)/弁護士
法的な問題について専門的なアドバイスが必要な場合、弁護士に相談することが有効です。日本弁護士連合会は地元の弁護士会を通じて法律相談を提供しています。また、法テラスは国が設立した法律援助の公的機関で、弁護士費用の補助を受けられる条件等について相談することができます。それぞれの相談先はその特性と役割により、ハラスメント問題に対する解決策を提供できます。問題の性質や自身の状況により、適切な相談先を選ぶことが重要です。
パワハラで謝罪や損害賠償を請求する方法とは
加害者や会社との交渉
交渉は、当事者間で直接行う場合、労働組合の団体交渉として行う場合、弁護士が代理人として行う場合などがあります。
労働災害補償の申立
ハラスメントが労働災害補償の要件に当てはまる場合は、会社から労働基準監督署に申立てることもできます。
ADR、行政の労働紛争調停等
弁護士会のADR、行政の労働紛争調停などを利用して相手方と話し合うこともできます。
労働審判
労働審判とは、労働審判法に基づき、地方裁判所で、個別労働関係民事紛争を、原則として3回以内の期日で解決する手続きです。訴訟に比べ手続きが簡略化され、迅速かつ柔軟な解決が期待できるという利点があります。労働審判の告知を受けた時から2週間以内に異議申立をした時は、通常の訴訟手続に移行します。
訴訟
裁判所に訴訟を提起することもできます。訴訟では、当事者が互いの主張と証拠を提示します。
裁判所は、被害者の請求に証拠に基づいて根拠があると判断した場合、加害者に謝罪や損害賠償を命じる判決を下します。