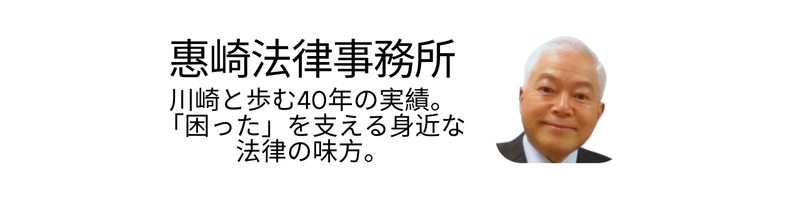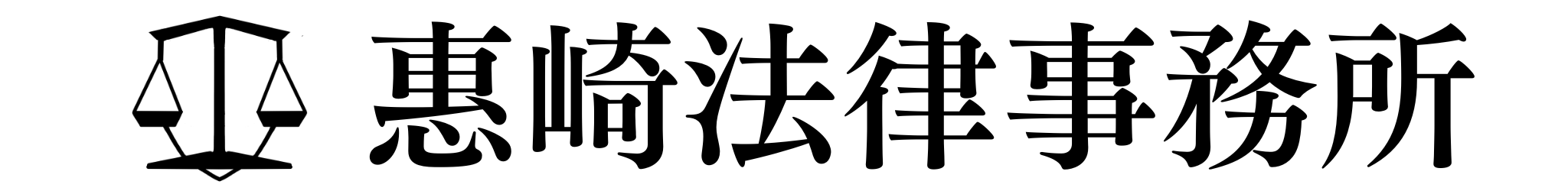最高裁判所第一小法廷 令和6(受)2 遺留分減殺請求事件
令和7年7月10日判決 原審、名古屋高等裁判所
1 ポイントは何か?
旧規定での遺留分代償金。
2 何があったか?
Aは平成19年に財産を全部Bに相続させる公正証書遺言書を作成し、平成
28年に死亡し、Bは上記遺言に基づきAの財産全部を相続し、不動産の相続
登記をし、預貯金の名義変更をした。
Cら他の相続人らで遺留分権利者らは平成29年にBに対し、遺留分減殺請求
権を行使する意思表示をし、不動産につき遺留分減殺を原因とする持分移転登
記手続及び預金の持分額の支払を求める訴えを提起した。
Bは、令和5年の高等裁判所での口頭弁論期日において、不動産につき、民法
旧1041条1項(令和元年7月1日施行平成30年法律第72号による削除
前の旧第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)1項「受贈者及
び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺
留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。」)に基づき、価額
の弁償をすることを通知した。
3 裁判所は何を認めたか?
Cら勝訴。最高裁判所は、Bに対し、Cらへ不動産につき遺留分減殺を原因
とする持分移転登記手続及び預金の持分額の支払を命じた。
Bは、不動産持分の価額弁償をして共有登記を免れることができなかったと
いう点において敗訴である。
判決文理由中に言う。
「遺留分権利者から遺留分減殺に基づく目的物の現物返還請求を受けた受遺者
が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示
をした場合において、遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利
を行使する旨の意思表示をしたときは、遺留分権利者は、遺留分減殺によって
取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権を遡って失い、こ
れに代わる価額弁償請求権を確定的に取得するが(最高裁平成18年(受)第
1572号同20年1月24日第一小法廷判決・民集62巻1号63頁)、遺
留分権利者が上記意思表示をするまでは、遺留分減殺によって取得した目的物
の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権のみを有するものと解するのが相
当である。」
これが、民法旧1041条1項の規定の最高裁における解釈であった。
4 コメント
現行法の遺留分権利者は、現物ではなく、遺産から一定の贈与、負債を控除し
た残存価額の遺留分割合分を取得し(1042条、1043条)、遺留分侵害額
の請求(1046条、1048条)により、受遺者、受贈者が負担する
(1047条)。これらの条文は、内容を細かく確認する必要がある。
したがって、現行法であれば、遺留分権利者は侵害額を請求するほかなく、裁
判所が認めることができるのも、金額の請求のみである。
しかし、1047条4項に「受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は
、遺留分権利者の負担に帰する。」とあるので、受遺者又は受贈者が無資力で
あることを証明すると、受遺者の請求は棄却されることになるであろう。例え
ば、受贈者が生活保護で、多額の医療保護費を贈与金で返還し無資力になった
場合などが想定される。但し、最高裁のHPの裁判例検索に「1047条4項
」で検索しても裁判例はまだ出てこない。