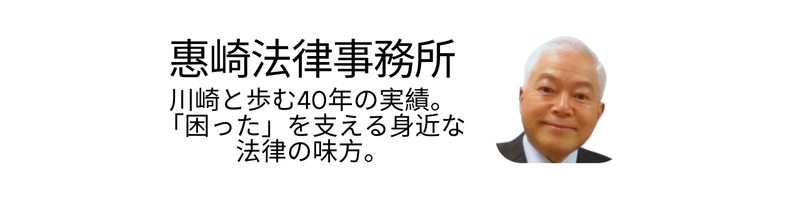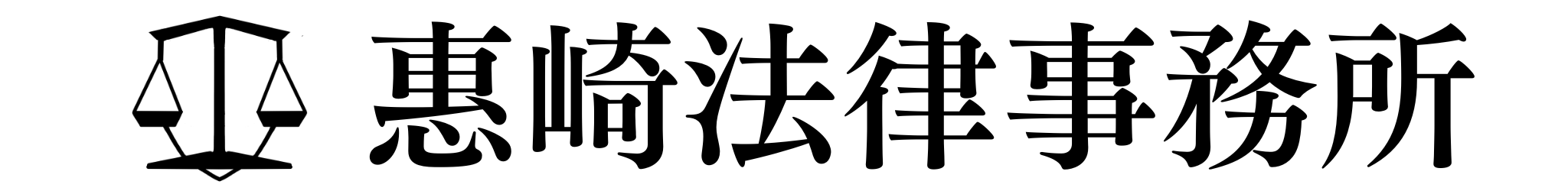最高裁判所第一小法廷 令和5(行ヒ)276 行政処分取消等請求事件令和7年7月17日判決(原審、東京高等裁判所)094297_hanrei.pdf
1 ポイントは何か?
介護保険給付優先の原則の下での障害者自立支援給付のあり方。
2 何があったか?
Aは、➀両下肢機能全廃及び両上肢機能の著しい障害により、1級の身体障害者手帳の交付を受け、➁市町村民税非課税世帯に属し、➂B市から自立支援法上、障害程度区分4(平成26年4月1日以降は障害支援区分4)の認定及び支給決定を受け、居宅介護を受けてきた。④平成25年12月には、居宅介護の支給量を身体介護月45時間及び家事援助月25時間、有効期間を平成26年1月1日から同年7月31日までとする決定(以下「平成25年処分」という。)を受けた。➄平成26年7月8日、行政Bに対し、平成25年処分と同じ内容の支給決定をするよう求める申請(本件申請)をした。
Bは、Aに対し、同月中に65歳に達するので、要介護認定申請を勧奨したが、Aが要介護認定申請をしなかったので、平成26年8月1日、Aに対し、本件申請を却下する処分(本件処分)をした。本件処分の理由は、総合支援法7条に基づき、介護給付との調整を行う必要があるところ、被上告人が要介護認定申請をしないため、介護給付の対象となるサービス(以下「介護保険サービス」という。)の量及び不足する障害福祉サービスの支給量を算定することができないというものであった。
Aは、本件処分の取消、支給決定の義務付け、国家賠償を請求する訴訟を提起した。
Aは、Bの勧奨に従って要介護認定申請をすると、自己負担分が生ずるという問題があった。
3 裁判所は何を認めたか?
原審東京高等裁判所では、A勝訴。境界層該当世帯に属する障害者は、支援措置事業により介護保険サービスに係る利用者負担の全額について補助を受けることができるのに対し、Aは、境界層該当世帯よりも収入の低い市町村民税非課税世帯に属するにもかかわらず、支援措置事業による補助を受けることができない。本件処分には、上告人においてこのような不均衡を避ける措置をとるべきであったにもかかわらず、これをとらなかったという意味において、裁量権の行使を誤った違法があるとした。
最高裁判所は、A敗訴とした。高裁におけるA勝訴部分を破棄し、高裁に差し戻した。
その理由は次の通りである。
⑴総合支援法7条及び総合支援法施行令2条は、介護給付を受けることができる場合には、その限度において介護給付を優先し、自立支援給付を行わないものとしている(介護給付優先の原則)。
⑵介護給付の訪問介護を受けた場合に利用者負担が生ずるが、支援措置事業の実施の有無により左右されるものではない。
⑶介護保険サービスに係る利用者負担についての補助の必要性は、市町村民税が課されるか否かの基準となる所得金額のみならず、これに算入されない収入や資産の状況、世帯構成等の諸般の事情によって左右されるものであるから、支援措置事業の実施によって、市町村民税非課税世帯に属する障害者と境界層該当世帯に属する障害者との間に、直ちに不均衡が生ずるということもできないので、Bが不均衡を避ける措置をとらなかったことを理由として、本件処分に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるということはできない。
⑷ 原審の判断には、市町村の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った結果、受けることができる介護給付のうち自立支援給付に相当するものの量を算定することができないとしたBの判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるか否かについて審理を尽くさなかった違法がある。
4 コメント
介護給付優先の原則はあるが、それは絶対的な原則と考える必要はなく、Aが介護認定を受けない以上、Bは、従前どおりの自立支援給付処分を行うという道もあったのではないか。Aは、平成26年処分以後、どうやって生活を維持したのだろうか。介護保険給付も自立支援給付も受けないとすると、障害年金と生活保護による補充だろうか。AとBのもっと柔軟で早急な話し合いによる解決もありえたのではないか。行政と住民の一般的な関係を見直すことも必要だ。