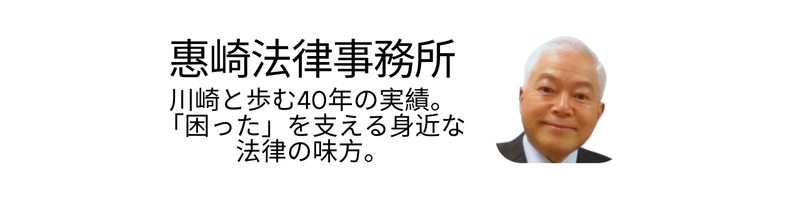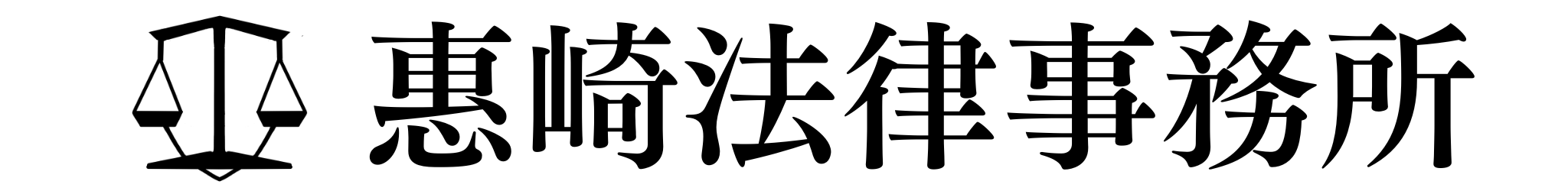最高裁判所第三小法廷令和6(あ)264窃盗、電子計算機使用詐欺、覚醒剤取締法違反被告事件令和7年7月11日判決、(原審、仙台高等裁判所)
1 ポイントは何か?
闇バイトの「出し子」と「架け子」の共謀の有無。
2 何があったか?
Yは、覚せい剤を使用・所持し(覚せい剤取締法違反)、また、闇バイトに加わり、氏名不詳者であるBらと共謀し、金融機関職員になりすましたBらが電話で、Aら7名に保険金を受け取るためのATM操作であると誤信させた上、実際はYらの管理する第三者名義の通帳に送金する操作をさせ(電子計算機使用詐欺)。Bらと共謀したYが、ATMで現金を引出した(窃盗)。
YによりATMから現金が引き出された窃取金被害総額は9,212,000円であり、これからYが報酬金として受け取った額は18万円くらいであるYは、残りの903万円くらいを、BらがYに指示したコインロッカー内に収めた。
検察官は、Yを、覚せい剤の使用・所持罪、窃盗罪、電子計算機使用詐欺罪等で起訴した。
3 裁判所は何を認めたか?
地方裁判所(懲役4年)→高等裁判所(懲役3年6月)→最高裁判所(懲役4年)
地裁は、覚せい剤の使用・所持罪、電子計算機使用詐欺罪、窃盗罪で懲役4年としたが、高裁は、地裁が電子計算機使用詐欺罪については、共謀が明白ではないとしてYを無罪とし、覚せい剤、窃盗罪について懲役3年6月としたが、最高裁は高裁判決を破棄し、控訴も棄却し、地裁判決が確定した。
BがAらを誤信させて、Aらの金を第三者の通帳に送金させる行為と、YがBらの指示でATMから現金を引き出す操作は、一連の詐欺・窃盗の犯罪を完成させるもので、手段と目的の関係にあり、Yには送金させる詐欺についても共謀が認められた。
(裁判官平木正洋の補足意見)
闇バイトの「出し子」らの「架け子らとの共謀」を認定する要件としては、「架け子らの中核的な行為態様(うそをつき人を欺いてその者に現金自動預払機を操作させて振込送金させる)の未必的認識」で足りるというべきであろう。
4 コメント
闇バイトは全く割に合わない。弁護人としては、暗証番号が盗まれて本人の知らぬ間に、銀行口座が利用され現金が経由されるケースに、共謀が認定されないように注意が必要。