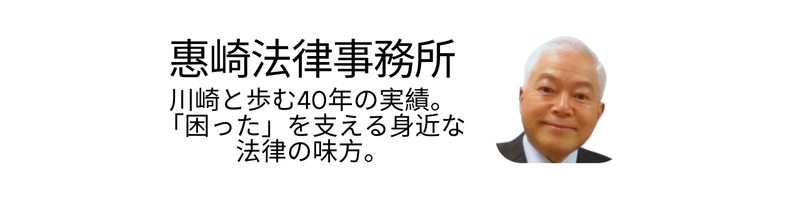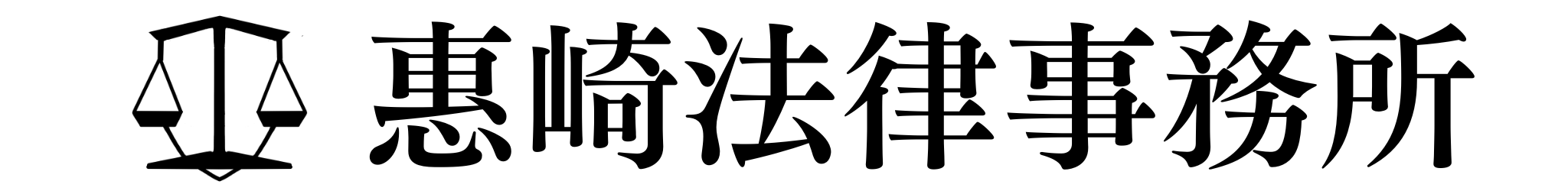1 ポイントは何か?
15歳少年の損害賠償責任、その親権者の監督責任の有無、損害金の算定等
。
2 何があったか?
Aは8歳ころから問題行動があったが、15歳当時の令和2年に第1種少年
院を退院後、更生保護施設を脱走し、商業施設のトイレ内で21歳の女性Bに
包丁を向け、自首を勧められたことに逆上して刺殺した。Bの母Cと兄Dが共
同原告として、A及びその親権者Eを共同被告として裁判所へ損害賠償請求を
した。
被告ら代理人は、Aには幼少時に受けた虐待により発達が阻害され本件事件
当時も現実感を喪失し行為の意味を理解する能力を欠き責任を負わないと主張
し、Bには監督義務違反がない旨主張した。またDは、父母や子ではないから
固有の慰謝料を請求する権利がないと主張した。
なお、Aは本件についての刑事事件(同裁判所令和3年(わ) 第62号)で
は懲役10年以上15年以下に処する旨の判決を宣告され確定している。
3 裁判所は何を認めたか?
地方裁判所は、AがCに対し5188万0640円、Dに対し220万円、
各遅延損害金3%を支払うよう命じた。Bの逸失利益は賃金センサスの同年代
の女性平均賃金をもとに5217万 5753円と算定し、精神的苦痛に対す
る慰謝料は3000万円とした。その合計額に相続分割合を乗じ、犯罪被害者
支援法による遺族給付金を控除し、弁護士費用をくわえたものがCに支払うよ
う命じた損害額である。
DはAと共に成長し助け合ってきた者として固有の慰謝料を認めた。
Eの責任は認めなかった。
4 コメント
Aには損害賠償責任の事実上の履行能力がないので、B及びCの勝訴判決は
当面、執行の方法がない。なお、民法711条の類推適用及びBに責任を科さ
ない判断は妥当。
政府の責任において、犯罪被害者支援法に基づく補償給付金を大幅に増額す
べきである。
Aの精神障害を認定すべきではなかったか。刑事事件で改善可能なものとも
考えられない。心理療法を受けながら働いて収入を得ることができる施設の拡
充を図らなければ問題は解決されない。